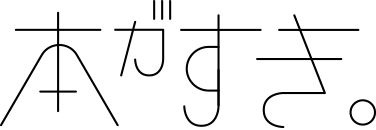2019/07/05
坂爪真吾 NPO法人風テラス理事長
『社会学史』講談社
大澤真幸/著

「構築主義や近代的主体の死、言語論的転回など、社会学の領域で取り上げられている理論や概念は、仏教の世界では数千年以上前から論じられていることだと思います。
それをあたかも最先端の理論であるかのように議論している社会学って、一体何なのでしょうか?」
大学3年の時に入った社会学のゼミの感想カードに、私は上記のような感想を書いた。
当時のゼミでは、構築主義に基づく言説分析=「何らかの実在や主体として信じられているものが、実は特定の時代(近代)の言説による構築物に過ぎない」ということを明らかにする議論や研究が扱われていた。
個人的には、そうした議論や研究には全く面白さを感じなかった。「そんなレベルの議論、仏教の領域(空の思想)で数千年前にやりつくされているじゃないか」と思っていた。
ドヤ顔で「●●という概念は、近代の構築物に過ぎない」と指摘しておしまい、という「なんちゃってフーコー」みたいな研究ではなく、「構築物であることを踏まえた上で、それらとどう向き合うか」という研究がしたかったのだ。
翌週のゼミ冒頭で、先生は「こんな感想もありました」と、私の感想を全員の前で読み上げた。
教室内がざわつき、「おいおい、誰が書いたんだ」「一体何を言っているんだこいつは」という先輩方の無言の怒りが伝わってきた。
こわばった空気の中で、私は先生がどんな回答をするのか、じっと待った。
先生は表情を変えずに、「確かにそうかもしれません。ただ、私の答えは、『Yes,but~』です」と静かに答えた。
確かに現代の社会学で論じられていることは、過去の宗教や哲学で論じられてきたことの焼き直しや縮小再生産に過ぎないように見えるかもしれない。しかし、決してそれだけではない。
残念ながら、この「but」の後に先生がおっしゃったことを、私は忘れてしまった。正確には、その当時の私には納得・理解できない言葉だったのかもしれない。
大学を卒業してから15年近く経った。学問の世界からは離れているが、社会学的なものの見方は相変わらず好きだし、社会学的な趣向を取りいれた新書を書く機会もある。
ただ、自分が社会学を体系的にきちんと理解しているとは到底思えない。著名な社会学者の名前や理論を引き合いに出して何かを語るような振る舞いもできないし、したくもない。「but」の先に何があるのかについても、未だに答えは出ていなかった。
そんな時、大澤真幸氏の『社会学史』を手に取った。著者の本は10代の受験生の頃から読んでいたのだが、大学を卒業してからは遠ざかっていたので、懐かしさと新鮮さが入り混じった感覚を覚えながら、ページをめくっていった。
本書はあくまで著者の視点と価値観から見た社会学史であり、他の著者が書けば全く違った社会学史が出来上がるはずだ。著者の視点や解釈に対する異論・反論も多いだろう。
ただ、学生の頃の私が社会学に期待していたもの、及び期待していたにも関わらず得られなかったもの、そして得られなかったと思い込んでいたにもかかわらず、振り返ってみれば得られていたことが、明瞭に言語化されて書かれている、ということは強く感じた。
もちろん、こうした感覚自体が、文中で紹介されているトマスの定理(=人がある状況を現実として定義すると、その状況は結果として現実になる)の表れに過ぎないのかもしれないが。
文中で著者は、学問には「直進するタイプ」と「反復するタイプ」の二種類があるような気がする、と述べている。
「直進するタイプ」は物理学などの自然科学系の学問であり、過去の説を捨てながら発展していく。「反復するタイプ」は、哲学のように、同じ問題に何度も何度も回帰しながら、螺旋状に進んでいく。
著者によれば、社会学という学問は、この二つの側面を併せ持っているという。
私自身、NPOの活動を通して社会問題の現場に関わる中で日々感じているのは、いわゆる「社会問題」の多くは、これまでに存在しなかった新しい問題では決してない、ということだ。
過去に解決しきれなかった問題、見逃され続けてきた問題が、時を経て再び「新たな社会問題」として私たちの目の前に現れることが圧倒的に多い。
だとすれば、必要なのはやみくもに新しい理論を追い求めることではなく、過去の理論を学び、徹底的に使い倒すことではないだろうか。それこそが、今日を生きる私たちが『社会学史』を学ぶ意義であるはずだ。
学生時代に分からなかった「but」の先にある答えは、現場と理論の間を往復しながら実践と思索を繰り返す中で、いつかきっと見えてくるに違いない、と考えている。

『社会学史』講談社
大澤真幸/著