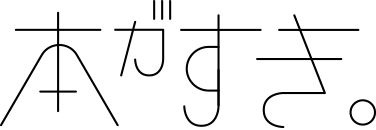2019/09/20
清水貴一 バーテンダー・脚本家
『人生で大切なことは泥酔に学んだ』左右社
栗下直也/著
酒を売って生計を立てている身として、本書はこの上なくありがたい一冊だった。誰が言ったか「酒は飲んでも吞まれるな」というお言葉があるが、そんなことを考えながら酒なんぞ飲めやしない。飲むならトコトン、連れに軽蔑されようが、記憶をぶっ飛ばそうが、トラ箱で最悪の朝を迎えようが、酒を飲む時間が至福の時、それがモノホンの飲み手である。もちろん後悔と猛省というおまけ付きだが、日没あたりには、性懲りもなく喉の乾きに誘われて、昨夜と同じ無限ループをくり返してしまうのである。

そうした酒仙の猛者たちが総勢二十七名のエントリーである。
時代に名を残した偉人たちの知られざる酒の失敗エピソードが満載の本書は、読後にじんわりとした安堵感を覚えるはずだ。わたしとしては、登場した方々に親近感を覚え、ひとり一人のエピソードの終わりには、「ナイスファイトです」とこぼし、次の先輩へと頁を進めた。
有名人、著名人の酒豪伝説や豪遊エピソードは世に多く知られている。ことわっておくが、ここに選ばれしは失敗談である。
物書きや俳優は、酒がよく似合う職業だ。太宰治、横溝正史、梶原一騎、河上徹太郎、小林秀雄、大伴旅人(笑)、掲載順に、中原中也、梶井基次郎、辻潤、梅崎春生、葛西善蔵、と物書きだけで十一人のエントリー。さすがである、まさにそうそうたるメンバーだ。俳優は二人と意外に控えめだけれど、世界の三船と、往年の銀幕スター原節子と両者ともビッグネームである。物書き、とくに作家や歌人はたとえ酒で失敗したとしても、その経験が作品に反映される。俳優だって芸の肥やしになっていくわけだから、ある種の武勇伝として語り継がれ、ハクがつくという意味で元が取れる。むしろ、中途半端に飲むほうが御法度の感が否めない。だが、政治家はそうはいかない。白壁王、藤原冬嗣、黒田清隆、米内光政、泉山三六、と、五名のエントリー。だが、無知なわたしにはまったくピンと来ない顔ぶれだ。それもそのはず、時代がまったく違う人たちだもん……と軽く言い訳してみる。
現代社会で酒での悪ふざけやトラブル沙汰を起こしたら、減給、謹慎処分、下手をしたらクビだろうし、プライベートだったと主張しても、ところ構わず動画サイトやSNSでアップされたりするとクビは間逃れたとしても信用問題に関わってしまう。飲み手には厳しい監視時代である。酒飲みにとっては、とくに重責な仕事に従事する人にしてみれば、飲むメンバーや場所には十分な注意が必要だ。
そんな面々から、わたしがもっともイメージを覆えさせられた人物は、福沢諭吉だ。「一万円の肖像の人」「慶応義塾の創設者」とおなじみの人物だ。
幼少の頃から酒好きで、母親に「酒を吞ませるから」となだめられ、嫌いな散髪に行っていたようである。正確な年齢が不明だったが、「嫌いな散髪」というニュアンスから推察すると、十歳前後の印象だ。早熟過ぎる目覚めではないか?
さらに諭吉は、飲むと全裸になる癖があったようで、ある日、酒を飲んで二階で寝ていると下女が下の部屋から声をかけてくる。寝起きで機嫌の悪かった諭吉は意地悪く全裸で降りていくと、そこには奥さんの姿があった。と、ほっこりエピソードがあった。奥さんの気持ちになって考えてみれば、こんな情け無いアホ旦那が、後に日本の紙幣の肖像になるとは考えもしなかっただろう。これを読んで福沢諭吉が大好きになった。
余談だが、諭吉のDNAはしっかりと受け継がれているような気がする。
慶応義塾、その優秀な大学の卒業生が、うちのお店の大学お客さん総数ランキングの上位にいることは間違いない。いちいちお客さんに出身大学を訊ねているわけではないが、なんとなく印象に強く残る飲み手が多いのは確かである。

昭和、平成、令和と時代の流れには逆らえないのだろうが、本書のような真の飲み手が減ってきたような気がするのは寂しいことだ。だが、この世から酒がなくならない限り、真の飲み手が絶滅することはない。たとえ「隠れノミシタン」となってもひっそりと生息し続け、わたしは彼らのグラスになみなみと注いでみせるのである。
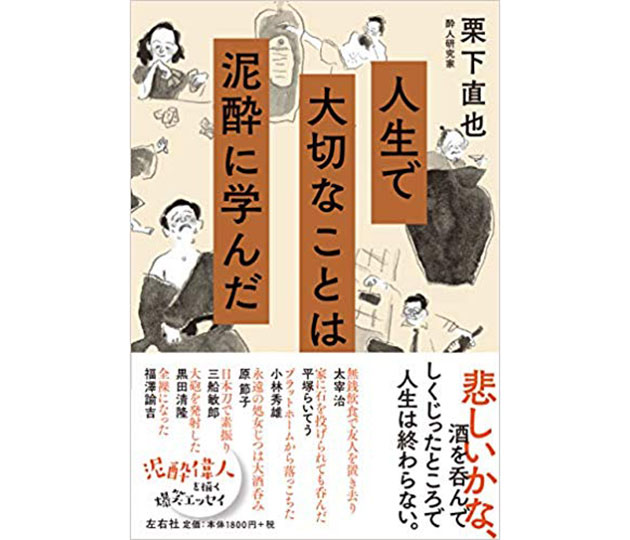
『人生で大切なことは泥酔に学んだ』左右社
栗下直也/著