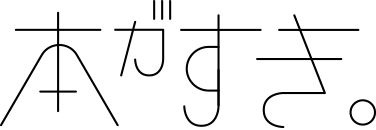2020/02/26
高井浩章 経済記者
『刑罰』東京創元社
フェルディナント・フォン・シーラッハ/著

各国で絶賛され、日本でも2012年の本屋大賞・翻訳小説部門トップに輝いた『犯罪』の筆者の最新作は、期待を裏切らない珠玉の短編集だ。『犯罪』と『罪悪』に2作を何度も再読してきたシーラッハファンの私にとっては、文字通り、待望の1冊。6月に入手して以来、お気に入りの収録作はもう3~4回読み返している。
ドイツで刑事事件専門の弁護士として活躍してきたフェルディナント・フォン・シーラッハは、自身が体験した事件を下敷きに創作を行っていると語っている。実際、多くの短編は司法システムと犯罪に精通した専門家らしい描写が作品を支える骨格として機能しているのは確かだ。
だが、私はこの説明を疑っている。実際にあった事件がヒントになっているかもしれないが、作品群の多くはほぼ純粋な創作物なのではないだろうか。弁護士が背負う守秘義務という重い足かせを考えると、実在のケースに着想を得てしまっては、ここまで深く人間の本性に踏み込み、人生の機微を描く作品は書けないのではないか。
私の仮説が正しかったとしても、それでシーラッハの作品の価値が下がるわけではない。もし3つの短編集のいずれも未読という読者がいたら、書店でどの1冊のどの短編でも良いから、拾い読みしてみてほしい。短い物なら数分で読める。どの一編をとっても、この作家の非凡さは伝わるはずだ。そして通読してみれば、この恐ろしく切れ味の良い短編を紡ぎ出す書き手の土台に弁護士として見てきた絶望と希望があることも明白だろう。
ほぼ純然たるフィクションだろうという仮説を持ち出したばかりではあるが、2編だけ、「著者の原体験に近いものではないだろうか」と思われる作品がある。『罪悪』収録の「ふるさと祭り」と『刑罰』の「友人」だ。前者は弁護士という職業が背負う業に直面した若者の成熟を、
過去2作に続き、簡潔な語り口の文体に仕上げてくれた酒寄進一氏の訳も素晴らしい。長くすぐ手が届く本棚の一角を占める1冊になりそうだ。
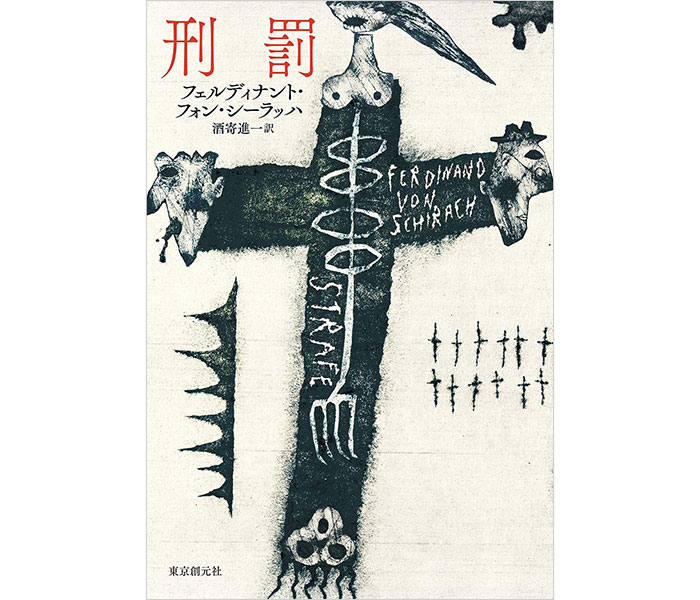
『刑罰』東京創元社
フェルディナント・フォン・シーラッハ/著