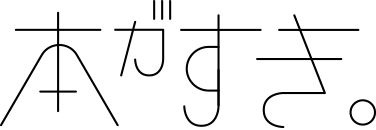2020/07/14
高井浩章 経済記者
『エリザベス女王』中央公論新社
君塚直隆/著

秀作ぞろいの中公新書の歴史シリーズのなかでも、指折りの傑作だ。今年で94歳、在位68年を迎えた「史上最長・最強のイギリス君主」の世界史的な位置づけ、そして何よりエリザベス女王自身と英王室メンバーの伝記として、きわめて秀逸な読み物になっている。
あらかじめお断りしておくと、ロンドンに駐在した影響もあって、私はエリザベス女王のファンだ。ご長命をお祈りしている。
その前提の上で白状すると、新聞記者は因果な商売で、ある程度の年齢に達した著名な人物については、その言動を「これは『評伝』に不可欠か否か」という視点で見てしまう。英エコノミストが「世界最高の雑誌」と評される一因は、巻末の「追想録」の人選と中身の素晴らしさにある。高い打率で「こんな評伝を書ければ記者冥利に尽きるだろうな」という力作が掲載される。
そんな記者の視点で見ると、この本は「ネタの宝庫」だ。どれだけの資料を読み込んだのかとあきれるほど、印象的なエピソードが目白押し。私には新書を読むとき、「ここは」と思ったページの角を折り曲げておく悪癖があるのだが、本書は数ページに一度のペースで「耳」が挟まり、上端だけ厚みが1.5倍ほどに膨らんでいる。
1つだけ本書中から逸話を紹介しよう。
時は1961年。この前年のいわゆる「アフリカの年」に、かつてイギリスの植民地だったガーナは共和制に移行していたが、政情不安で治安が悪化していた。英政界では、予定されていたエリザベス女王の訪問への危惧の声が上がる。
だが、国際政治の観点から見ると、当時のガーナは冷戦下で米ソが綱引きを演じる戦略的な重要性を持っていた。女王が訪問を中止すれば、ガーナは東側陣営になびいてしまう恐れがあった。
爆弾騒動まで起きるなか、エリザベス女王は首都アクラに乗り込み、大歓迎を受ける。
その日の日記に当時のマクミラン英首相はこう記す。
「女王はまさに男の心臓と胃を持っていらっしゃる。(中略)彼女は操り人形(パペット)などではなく、女王(クイーン)なのだ」
こんな調子で、鳥肌ものの逸話が次々と出てくる。あとは読んでのお楽しみとしよう。
無論、こうした逸話を蒐集した作者の労を多とするところではあるが、破格の面白さはそれだけエリザベス女王の歩んだ道が波乱に満ちていた証左であろう。
図表と写真も選りすぐりで、要所では原典からの引用がなされている。よくぞ新書サイズにこれだけの情報量を盛り込んだものだ。
それでいて文章は簡潔で、詰め込みすぎの窮屈さはない。読者の関心が高いであろう日本の皇室との関わりの記述が手厚い。個人的には勉強不足だったコモンウェルスの実態とその運営への女王のコミットメントの部分を興味深く読んだ。
本書はハリー王子・メーガン妃の婚姻までをカバーしている。その後、このカップルが王室から「離脱」することになったのはご存じの通り。現在進行形のドラマをウオッチングするうえでも、第二次大戦前から続くエリザベス女王の治世を振り返ってみてはどうだろうか。英王室に限らず、20世紀の歴史に関心のある人なら、手に取って損はない一冊だ。

『エリザベス女王』中央公論新社
君塚直隆/著