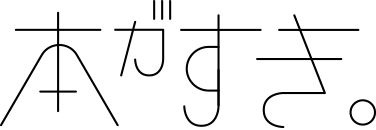2018/09/10
清水貴一 バーテンダー・脚本家
『知ってるつもり 無知の科学』早川書房
スティーブン・スローマン&フィリップ・ファーンバック/著
土方奈美/訳
広辞苑で調べてみると無知とは、「知識のないこと」「おろかなこと」とあった。そして、その無知を科学したのが本書だ。
はじめまして、バーテンダーの清水です。わたしは、あまりモノを知らない。つまり、本書の中に出てくる無知な存在そのもので、自分のおろかさを感じつつ、時には一縷の希望のようなものを掴みとりながら読み進めることができた。
わたしはバーを営んで20年ほどになる。言い換えれば、酒を飲む人々と20年ほど、関わっている。現在、世界がどこへ向かおうとしているのか、テクノロジーの進化や人口過多の果ての未来のことなど、知る由もない。

バーテンダーの仕事の大半は、店の空気を読み、お客様の気持ちの流れを心地よく作ることだ。それは麻雀の牌パイのようにまったく同じ日はひとつとない。とはいえ、無知と知というくくりでこの20年を振り返った時、お客様の側にも大きな変化がある。例えば、かつて昭和時代に絶大な人気を誇った「物知りおじさん」。無知な若い客やバーテンダーを捕まえては(わたしも含む)噓か真かもわからぬ話を、おもしろおかしく雄弁に杯を重ねていた。われわれは、物知りおじさんが来ると、あれやこれやとなんでもたずね、彼らも満足げにそれに応えてくれた。それが今や、スマホで簡単に調べることができる。おじさんの話の正誤がすぐにバレてしまうのだ。本物の物知りおじさんならいいが、偽の物知りおじさんはたまったもんじゃない。こうして、偽おじさんは、時代と共にお口にチャックを余儀なくされた。さみしい話だ。乱暴な言い方だが、作り話だろうがなんだろうが、語る内容がおもしろければよかったのに。教科書やインターネットには載っていない情報を聞けることが、人へ関心を抱く理由なのだから。
本書の第一章に、元アメリカ国防長官D・ラムズフェルドの言葉が引用されている。これがすごく心に刺さった。
「世の中にはわかっているとわかっていることがある。これは、自分たちにわかっているという事実がわかっていることだ。一方、わかっていないことがわかっていることもある。つまり、自分たちにはわかっていないという事実が、わかっていることだ。しかし、わかっていないことがわかっていないこともある。自分たちにわかっていない事実すら、わかっていないことだ」
この三つの中で、先の二つに対する自覚は誰にでも漠然とあるだろう。しかし、なにより厄介なのは、「わかっていないことがわかっていないこと」だ。これは、自分にも他者にも無関心に近い。だが、これの対策はある。先に述べた「関心を持つ」ということだ。わたしの場合は、人(お客様)に関心を持ち続ければ、わからなかったことが少しでもわかり始めるはずだ。
そして、本書の著者であるふたりの認知科学者はこういう風に述べている。知性(賢さ)はIQによって測られてきたが、知的な営みは「個」ではなく「集」にある。人知を越えた偉業には、必ずそれを支える賢いスタッフがいる。それこそが、目的の為の共有力と関心力を持って貢献する、本当の知性(賢さ)ではないかと。
その言葉に習うなら、バーとは、わたしを含むスタッフさえしっかり頑張れば良い店ができるわけではなく、お客さんも一丸となって楽しまなくては良い店にはならないということだ。つまり、ひとり一人が「楽しむ」ことを共有し、少しずつ「楽しい」に貢献をしていくことが、それがたかが酒場であっても知性ある場になりうるのだと、学ばずにはいられない。
読み終えて、ほんの少しだけソクラテスの「無知の知」に近づけた気がした。こんなに脳を刺激してくれる本はなかなかない。

『知ってるつもり 無知の科学』早川書房
スティーブン・スローマン&フィリップ・ファーンバック/著
土方奈美/訳