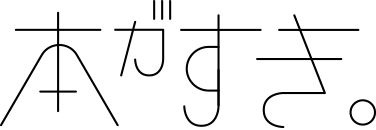2019/07/26
小説宝石
『椿宿の辺りに』朝日新聞出版
梨木香歩/著
化粧品会社の皮膚科学研究所に勤める三十代の山彦(やまひこ)、本名・佐田山幸彦(さたやまさちひこ)は、〈痛みというアラームが体に鳴り響くと、(略)存在の基盤、のようなものが崩れ落ちそうになる〉ほど痛みに弱い体質らしい。
山彦には、名前から連想するなら海彦という兄がいるはずだが、実際にいるのは二つ年下の従妹・海幸比子(うみさちひこ)で、彼女は海子を通称にしている。山彦はある夜から、肩から腕にかけて痛み始め、よくなる兆しはない。海子も原因不明の痛みで困っているところで、よく効くという鍼灸院(しんきゆういん)を紹介してくれた。
それと前後して山彦のもとに、実家の店子(たなこ)である鮫島(さめじま)の家から賃貸契約解消を申し出る手紙が来る。差出人の名前は「宙彦(そらひこ)」。古事記に描かれた神話では、山幸彦の別名が虚空津彦(そらつひこ)であるらしいが、それが物語の背骨になっていくことは予感される。
山彦の祖母はお別れのときが近づいているというのに、佐田の屋敷の後始末を気にしていて、そこにある稲荷を詣(もう)でるように祖父の藪彦(やぶひこ)から託されたと話す。驚くことに、海子が紹介してくれた仮縫(かりぬい)鍼灸院でも、仮縫氏の双子の妹・亀子(かめし)が特別な能力を使い、藪彦からの同じメッセージを受け取っていた。仮縫氏は、そこに山彦の痛みを解く何かがあると語る。かくて山彦は、亀子を伴い、祖先の家がある椿宿(つばきしゆく)へ向かう。
その旅先で、山彦が出会う数々の逸話を読み進めていくと、物語は表層から深層へ、長らく隠されていた屋敷で起きた藩主一家の惨劇や、椿宿の地形や自然に根づいたいくつもの悲願を浮かび上がらせていく。それはやがて人が痛みを感じる意味や人生における痛みの処し方といった、含蓄のある悟りへと読者を導くのだ。既出作『f植物園の巣穴』とも思いがけない形でつながるが、本作だけでも面白い。
こちらもおすすめ!
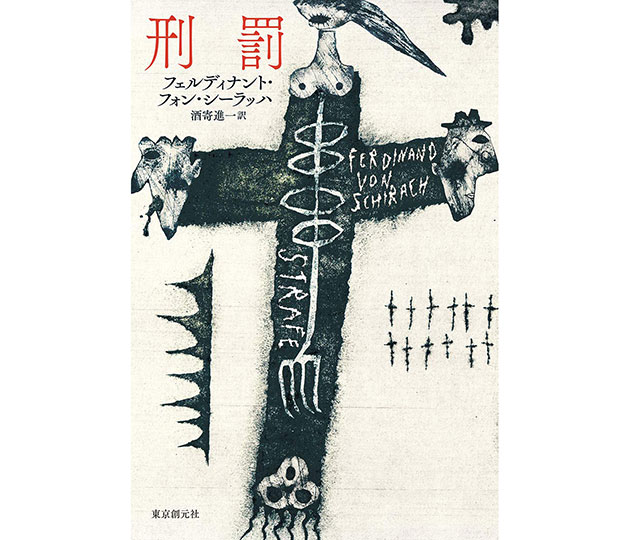
『刑罰』東京創元社
フェルディナント・フォン・シーラッハ/著 酒寄進一/訳
シーラッハ犯罪事件簿三部作の最終巻
シーラッハは、市井(しせい)の人々が犯罪に手を染めたり巻き込まれたりするときの、ふとしたきっかけとそこに至る背景とを書き続けてきた弁護士作家だ。本書は『犯罪』から続く短編集シリーズ最終巻で、十二話を収録。盲点を拾い上げ真相を見抜く相変わらずの面白さに舌を巻く。また、本書は初めて、自身が書くことを始めた動機になった、司法による刑罰は加害者の救済になることもあるとわかる事件をもとにした一作が入っている。何らかの形で非業(ひごう)の死と関わった者の孤独感と疎外感を、抑えてもあふれ出す強い筆致で綴っており、ファン必読の一冊だ。

『椿宿の辺りに』朝日新聞出版
梨木香歩/著