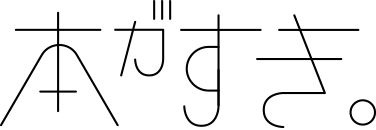2021/01/21
藤代冥砂 写真家・作家
『新型コロナはアートをどう変えるか』光文社
宮津大輔/著

「最も強いものが生き残るのではなく、最も賢いものが生き延びるのでもない。唯一生き残ることができるのは、変化できるものである」という適者生存の法則は、この新型コロナの時代によく見かける言葉だ。
暮らし方、働き方が、この病原菌によって大きな影響を受けていることは、経済的な側面だけでなく、精神面においても明らかで、たとえこの事態が収束を迎えたとしても、元には戻れない変化を引き起こしていると考えている人は多いと思う。
この環境の変化が、もしも局地的な、たとえば日本だけに蔓延した風土病を原因とするものだったら、おそらく私たちは従来の暮らし方、働き方に戻ることを大きな共通の目標とすることを願ったかもしれない。ワクチンを開発するなりして、病原菌に打ち勝ち、科学の力をさらに信奉して、これまでの進化に対して自信を深めていったことだろう。
ただ今回の環境の変化は、地球規模のものであり、間違いなく人類全体がみんなで背負ってしまった課題となっている。規模の大きさは、言うまでもなく事の大きさであり、今回の出来事は稀にみる大きさで、私たちを飲み込んでいる。
そして、アフターコロナにある未来像は、三密を避ける生活基盤を想定しているはずで、新型コロナのような病気が蔓延する可能性がこれからもある以上、働き方と暮らし方が刷新されざるを得ないし、去年からの生活の揺らぎは、今後、結構しっかりと人々に記憶されていくと思う。

そんな変化の途上になるこの時代において、コロナ以前にはオークションベースで七兆三千億円(2018)もあったアート市場について、論じたのが本書だ。
ペストや黒死病の時代から現在に至るまで、疫病をアートはどう扱ってきたのかという史的考察から始まり、コロナ時代のアート市場の予測や、こらからのアートとアーティストの在り方についてまでをも視野に入れている。
言うまでもなく、この世界は資本主義の世界であり、それは、人口あたり0.7パーセントの富裕層が、保有資産額で全世界の約半分を持っているという世界を生むに至っているのだが、アートを経済的に支えているのは、この富裕層であり、この富裕層がいる限り、アートが衰退することはないと本書は断言している。
そもそもなぜ富裕層はアートを集めたがるのかというと、それは、容易に到達できない自己の成功や莫大な資産を可視化し、単純な物欲に代わって満足感を提供し得るのが、フィランソロピーやアートコレクションだからだ。もちろん、ステイタスを満たすだけでなく、投資対象としての価値もある。そんなアートだからこそ、中国のビリオネアたちもロンドンとニューヨークに続くのである。
今やアメリカ、イギリス、中国の三国で全世界のアート市場の90パーセントを占めるなか、私が不思議に思うのは、なぜ日本はその一角に食い込む力がなかったのか、ということだ。
別に、日本に食い込んで欲しいわけではないのだが、経済力の比率で言えば、世界のわずか1パーセントしか占めない地位の低さは、不自然のように思えるし、歴史的に見た日本美術の位置の高さからしても、また一般的な審美眼の高さからしても、なんとも不思議でしかたない。

もともとアート市場というのは、白人文化のものであるし、本来日本から見たよその文化に従う必要はないのだが、チャンピオンベルトがその社会に属している以上、そこを獲りにいこうとするのは、格闘技の世界でもそうであるように、そんなに不自然なことではないのかもしれない。ラスベガスのリングに上がるようなものだからだ。
だが、個人的には、こんなに世界が変わろうとしているのに、従来のプレイヤーが大手を振るうアート市場を目指そうとするのはなんとなく萎える。むしろ、数億年で自分の作品がオークションで落とされるのを夢見るよりも、アーティストとコレクターがささやかに直に、無農薬野菜を売買するような市場が膨らむ方がいいなと思う。
ダヴィンチの絵が史上最高額の460億で落札される一方で、隣の6年生が描いた絵が、50万円で売れる世界もいいなと思うのだ。

で、本書のいいところは、アートを目指すのなら、市場が小粒な日本からは出た方がいいなということを自然に思わせてくれるところだ。ここでの成功は瓦版みたいだと実感させてくれる。
ネットで繋がっていれば、どこでも暮らせるとは誰もがいうが、住む場所をどこにするかで、その後の暮らしは大きく左右される。
ウィズ、そしてポストコロナの時代には、変化できるものが生き残るとされている。変化というのは、とどのつまり、出生地を離れることだろうと、出生国を離れて、異言語で生きるということだろうと本書で改めて考えさせられた次第。

『新型コロナはアートをどう変えるか』光文社
宮津大輔/著