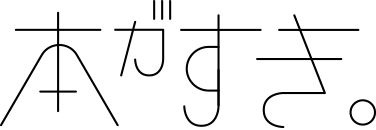2021/02/18
藤代冥砂 写真家・作家
『時間とテクノロジー』光文社
佐々木俊尚/著
人はなぜ生きるのか?
この問いは、人類の持つ生まれ出る悩みとして、面々と受け継がれてきたものと言えるだろう。
とても根源的な疑問であるのだが、それについて深く考えたり悩んだりするのは、人の一生において青春と呼ばれる時期がピークで、家庭を持ち、日々の営みに時間を取られるうちに、考えもしなくなる。
だが、それでも人生の節々において、古傷のように疼く時もある。大抵それは不遇な時であり、その時の苦しみを解消しようと根源的な問いと向き合うことになる。
そして、答えなど出ないまま、またその問いから遠ざかる、というのを繰り返していく。
その答えを、本の中に探そうとする時には、宗教書、自己啓発書、思想書などを手に取ることが多いだろう。書店の書棚に並ぶそれらを眺めて、これはという一冊を手に取りレジへと向かう。もしくは、スマホのボタンを押す。
だが、「人はなぜ生きるのか?」という大きな大きな問いに対する答えを教えてくれる本というのは、なかなか存在しない。なんとなく腑に落ちたような、落ちないような感じで読了して、まあいいか、と生活とやらに復帰していくことになる。
今回紹介する本の「時間とテクノロジー」という科学エッセイ的なタイトルは、どことなく無臭なイメージがあって、「人はなぜ生きるのか?」について書かれている本のようには見えない。文系な問いに、理系の佇まいが違和感すら感じられる。
だが、この本には確実にそれへの答えが提示されている。帯からの引用してみよう。「深層学習、環境知能、ナッジ、VR、AR、……最新の学問と技術から考察した「新しい人間哲学」ここに誕生」
つまり、最新の科学と、それの影響による生活スタイルの変化を視野に深く入れつつ、これまでの人類と、これからの人類について、そして、「人はなぜ生きるのか」の問いへの答えまで語られているのが本書だ。
最新の科学的な知見を視野に入れつつ考察されていく人類の歩みとこれからは、見えないものを信じることを前提としておらず、スマホやそれに続く生活様式の変化を捉えている身近さもあって、現実感を失うことなく読み進めていける「人はなぜ生きるのか」本となっていて、読者を立ち止まらせることなく、遠くへ遠くへと知的に誘ってくれる。
さて、そろそろ、ネタバレになり過ぎない程度に、本書を要約してみたい。
人類は、時系列の因果にそった方法によって世界を理解してきた。過去、現在、未来という時間軸上にのみ世界は存在しているとみなし、文明を発達させてきた。過去よりも、今日、今日よりも未来にこそ、進化進歩した明るい世界が存在すると信じ、日進月歩の努力を重ねてきた。時系列に沿って、発展していくこと、それができると信じて、一方向を向いて生きてきたわけだ。
だが、それは常に人生の目標やゴールを強制される世界でもある。停滞は怠惰や生きることへの放棄と見做されて、疎まれてしまう世界だ。
だが、取り憑かれたように未来へと発展していこうと生きるのは、結構しんどい。それは実は自由な選択ではなくて、川に流されているようなものだ。私たちは、テクノロジーの発展による生活の自動化によって、目標設定やゴールを抑圧と感じるようになり、新しい生き方や哲学を必要とする。遠くない未来においては、想念だけで現実が動き、仮想と現実の境が消失するので、古色蒼然とした時系列の因果の物語がフィット感をなくすのだ。
人は何かを成し遂げるために、何かの目標のために生まれ生きる、というのは一つの古い信仰のようなもので、時系列の因果の物語は古典的なものになるだろう。そういう世界では、「人はなぜ生きるのか」という問いすらが古い時代のものとして風化してしまう。
そもそも人は、生きているからこそ生きているのであって、過去も未来も現在も、実はなくて、「生きよう」と思った瞬間に「生」はただ起動する。これは、ハイパーサイクルとオートポイエーシスの理論によって説明されていることだ。
ただ、これは今だけ良ければいいという刹那的なものではない。生命は時間軸に沿った長期的な目的を検討しているのでなければ、刹那的に一瞬でも生命が燃焼すればいいと考えているのでもなく、ただこの生が続いてき、この生を維持し続けていくということを求めている。ただそれだけのことだ。
ざっと要約してみたが、つまりは、生きる理由などなく、生きるから生きるのだ、というような禅問答みたいなことになる。それを科学的知見で証明していっているのが本書である。
個人的に、最近、科学と仏教の近さを感じることが多いが、ここでもそれを感じた。
わたしたちは、整列して同じ方向へと向かうような生き方から離れて、今日を生きることに立ち帰り、意味を求めずに、淡々と粛々と機嫌良く生きることが素敵なのではないだろうか。そんな語りかけをしてくれる本書を読み終えて、淡い肯定感に包まれるのを感じた。

『時間とテクノロジー』光文社
佐々木俊尚/著