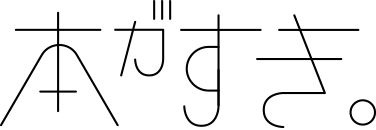2021/04/19
馬場紀衣 文筆家・ライター
『改良』河出書房新社
遠野遥/著

人間の価値は外見の美しさだけで決まったりしない。「美しさ」よりも大切にされるべきことが他にもたくさんあるはずだから。しかし、この考えは本書の主人公にとっては説得力をもたない。
主人公の「私」は、美しくなるために努力をする男子大学生。コールセンターのアルバイトで理不尽な客を相手にお金を稼いでは、美容とデリヘルに費やしている。自分らしくありたい、そのために美しさを求める「私」は、ウィッグをつけて、カラーコンタクトを装着し、メイクと服装で姿を変える。お気に入りはライチの香りがするハンドソープだ。
「女の格好をした私が鏡に映った。ランプの薄明かりの中で見る私は一層きれいで、私は私から目が離せなくなった。他人と一緒にいるせいか、私は私の知らない表情を浮かべていた。私は不意に、ずっと探していたもの、あるいはそれに近いものがこの鏡の中にあるように感じた。これがあれば、ほかのものはいらない気がした。」
しかし、いくら美容にお金をつぎ込んでも、オシャレを研究しても、スキンケアに詳しくなっても、彼女たちには遠く及ばない。もっと女性らしい仕草を真似て努力を重ねれば、あと少しくらいは美しくなれるかもしれない。けれど、自分には限界があることも分かっている。
「私は彼女たちが手にしているものが美しさだけではないことを思い、しかしその多くは美しさをうまく活用することで得られたものだと考えた。一方で、醜く生まれた私には美しく生まれた人間のことなど理解できず、見当違いのことを考えているのかもしれないとも思った。」
「私」と彼女たちは、おなじ生きものであるはずだ。歳もそれほど変わらない。それなのに、どうしてこれほどまでに自分と彼女たちとのあいだに差があるのだろう。なぜ自分には美しい顔や美しい脚がないのだろう。
たとえば主人公は、指に生えている毛を剃るべきか残すべきかで悩んだりする。誰も「私」の手に毛が生えているかどうかなんて気にしないかもしれない。それに自分は彼女たちとちがって、明日からも社会では男性として生きてゆかなくてはならないのだ。毛がなかったら不自然に思われるかもしれない。「どうして女性と男性とで、かくあるべき姿というのが違うのだろう?」主人公はそう自問する。
「女たち」は、自分よりもずっと美しい。美しくなりたいと望む主人公にとって、人間の価値なんてものはどれも美の前では霞むように思えてならない。主人公の「女になりたい」欲望と、それによって引き起こされる性をめぐる暴力から浮かび上がってくるのは、社会の同調圧力のひとつでもある「美」の息苦しさだ。そして普通や当たり前だと思われていることが、実はそうではないことを気づかせてくれる。
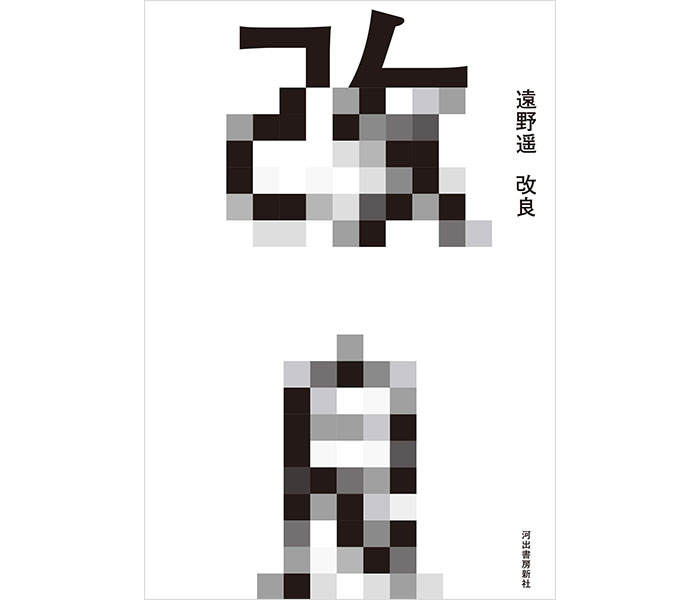
『改良』河出書房新社
遠野遥/著