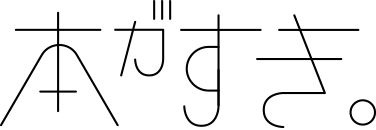2021/07/30
長江貴士 元書店員
『重力波は歌う アインシュタイン最後の宿題に挑んだ科学者たち』早川書房
ジャンナ・レヴィン/著 田沢恭子、松井信彦/翻訳

本書は、「重力波とは何か?」という理論的な話ではなく、むしろ「重力波はどのようにして検出されたのか?」という人間の物語です。しかしやはりまずは、重力波とは何なのかという話から始めましょう。
重力波の存在を予測したのは、あのアインシュタインです。重力波の検出は、「アインシュタイン最後の宿題」と呼ばれ、アインシュタインが相対性理論を発表した1915年からちょうど100年後の2015年に検出されました。
アインシュタインは相対性理論によって、時空(時間と空間)や重力の概念を変えました。それまで重力というのは、「物質を落下させる力」程度にしか捉えられていませんでしたが、アインシュタインは重力を「時空の歪み」であると捉え直しました。
どういうことでしょうか?例えば天体について考えましょう。質量が重い天体ほど重力が大きい、ということは知っていると思いますが、それは一体どういうことでしょうか?
ここで、大きなシーツの四隅を4人で持ってピンと張った状態を思い浮かべて下さい。そのシーツの上に、ボウリングの球を載せます。すると、重いボウリングの球はシーツの上で沈み込むでしょう。この時のシーツの沈み込み(=時空の歪み)を「重力」だとアインシュタインは考えたのです。
何故「時空の歪み」が「重力」になるのか。例えば、ボウリングの球を載せた状態のシーツの端の方に、テニスボールを載せるとしましょう。するとテニスボールはシーツの沈み込みに沿って動いていき、やがてテニスボールはボウリングの球のところまで行き、ボウリング球の周りをしばらくグルグル回るでしょう。これが、大雑把な地球と月のモデルです。こんな風にして、「重力」が発生するということを、「時空の歪み」と捉えることが出来るのです。
そのことを踏まえた上で、また別のことを考えてみましょう。同じようにしてピンと張ったシーツの上に、上から勢いをつけてボウリングの球を落とすとしましょう。この時、ボウリングの球はシーツの上で何度かバウンドし、さらにシーツも上下に揺さぶられるでしょう。この「シーツの上下の揺さぶられ」を「重力波」と呼ぶわけです。つまり、「重力が発生することで時空が歪み、その歪みが波となって伝わったもの」が「重力波」というわけです。
この重力波、提唱したアインシュタイン自身が「恐らく検出は不可能だろう」と言ったとされます。何故か。それは、重力波があまりにも小さいからです。
重力波は当然、大きな重力が発生すればより大きくなるので、まずは宇宙空間で非常に大きな重力を発生する現象を探しましょう。例えば、二つのブラックホールが衝突する、という場合を考えてみます。この時に放出されるエネルギーは「太陽10億個分の一兆倍を上回る」そうです。全然イメージ出来ませんけど、とにかく凄そうですよね。しかし、そんなメチャクチャ大きな重力が発生しても、地球で観測される重力波は、「地球と太陽との間の距離が、水素原子1個分伸び縮みした」ぐらいの変動しか引き起こしません。これも全然イメージできないでしょうけど、なんかめっちゃ小さいんだな、ぐらいのことはわかりますよね。
これほど小さな重力波を検出するために、LIGOという実験装置を作り上げた人たちがいました。これは、2億ドル以上のお金を掛け、1000人以上の科学者が関わる超大規模なプロジェクトです。そんなプロジェクトに深く関わった人物たちを描き出すのが本書なのです。
メインとなるのは、ライナー・ワイス、キップ・ソーン、ロン・ドレーヴァーの三人です。ワイスは「重力波」を検出するための「俳句のようなシンプルな干渉計」を思いつき、ソーンは「重力波」を理論的な側面から攻め、ドレーヴァーはお金の掛からない独創的で天才的な実験を次々に生み出していました。彼らは、「重力波」どころか、ブラックホールすらまだ実在が懐疑的とされていた時代に、いかにして「重力波」を検出するかをそれぞれ独自にアプローチしていきます。しかし、重力波のあまりの小ささに、彼らは手を組むしかないと判断するのですけど、そう簡単にはうまく行きませんでした。チームワークは最悪、人間関係のトラブル続出、プロジェクトに関わり続けられなくなった人間も出てくるほどゴタゴタしてしまいました。
その理由は、2億ドル以上という膨大なお金も関係してきます。科学の研究資金の確保は、政治とも関わってくるからです。「研究者」と「政治」は相当に馴染まないものですが、重力波検出を成し遂げるためには「政治」を無視することは出来ません。そんな風にして、多くの人間が関わり、また去っていき、そういう混沌とした状況の中で、次第に研究環境が整い、やがて重力波の検出という世紀の大発見をもたらすことになるのです。その過程がドラマティックに描かれる一冊です。
よくこういう研究の成果が発表されると、「それだけ膨大なお金を掛けて重力波を検出して、どんな役に立つんだ?」と聞く人間が出てくるものですが、僕はそういう問いに意味はないと考えています。何故なら、「科学的な発見」が「実用化」されるまでには時間が掛かるものだからです。
相対性理論も、あるいは相対性理論と並んで20世紀の二大物理学である量子論も、生み出された当初は実用化される可能性などまったく考えられなかったでしょう。相対性理論は天体の動きに当てはまる理論だし、量子論は原子などに当てはまる理論であり、日常的な話と関係しなさそうです。しかし今では、相対性理論は人工衛星からの情報(GPSなど)を補正するためには必要不可欠だし、量子論は電子回路を作成するのに必須です。重力波が今後どのように発展していくのか誰にも予測できないし、もしかしたら未来では重力波の発見が僕らの生活を激変させる何かに使われているかもしれません。もちろん、貧困や差別など、世界で発生している喫緊の問題にお金を回すべきだ、という意見はあるでしょうが、それは政治の領域の問題だと僕は思っています。研究資金が出され、研究が行われることになったのであれば、そこから生まれた成果は、それがすぐに大きな貢献をもたらさなかったとしても、好意的に受け止めるべきではないか、と僕は感じてしまいます。
重力波の検出は、2017年のノーベル賞を受賞しましたが、その受賞は異例だったといいます。3人の受賞者の内2人は、本書にも登場する、重力波の発見に科学的な見地から貢献した人物でしたが、残る1人は、LIGOの所長であり、いわば「管理職」のような立場の人なのだそうです。彼は重力波については門外漢でしたが、「彼がLIGOの建設や組織運営に携わらなければ、重力波はまだ見つかっていないだろう」という理由で受賞となったようです。理論を組み上げる理論物理学者(アインシュタインのような人)ならともかく、実験物理学は益々大規模になっていくでしょうし、そういう中で、組織運営をする者が正当に評価されるというのは、とても良い流れであると感じます。
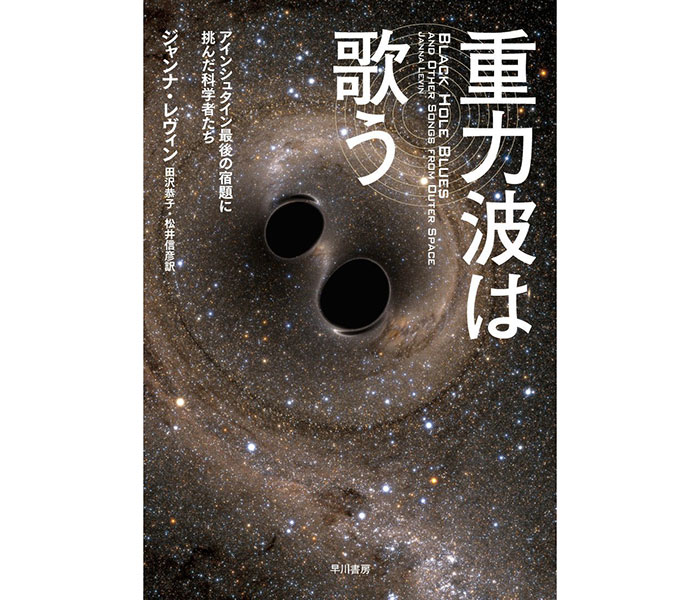
『重力波は歌う アインシュタイン最後の宿題に挑んだ科学者たち』早川書房
ジャンナ・レヴィン/著 田沢恭子、松井信彦/翻訳